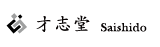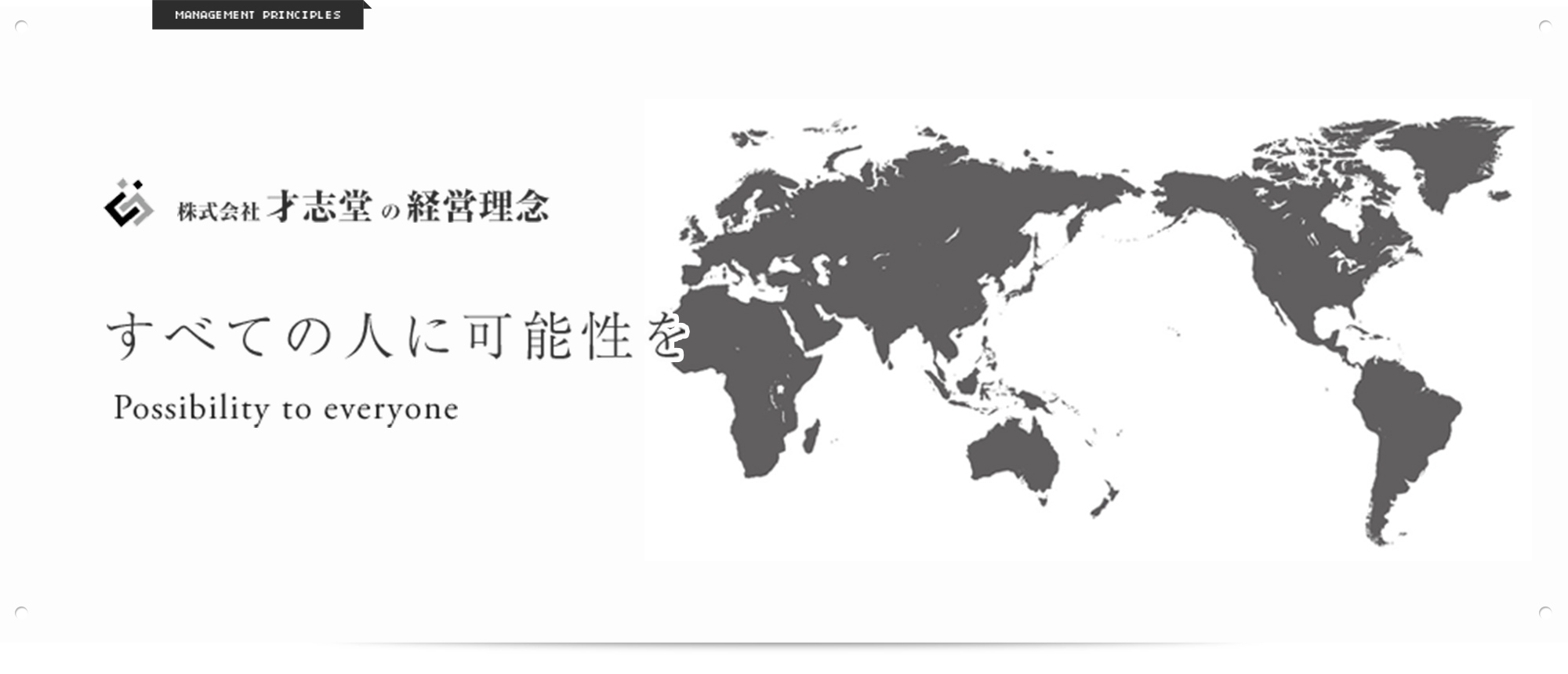News Release
- 2023.03.08
- 【お知らせ】メディアリンク株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:松本 淳志)との間におきまして株式譲渡契約を締結し、メディアリンク株式会社のグループ会社(100%子会社)となりました。
- 2023.03.01
- 【お知らせ】松井 雄樹が代表取締役社長に就任致しました。
- 2021.11.29
- 【冬季休業期間】2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月) の期間、誠に勝手ながら冬季休業とさせていただきます。
- 2021.03.23
- 【お知らせ】エンジニア・営業職のユニーク採用をはじめました。
- 2020.11.26
- 【冬季休業期間】2020年12月29日(火)~2020年1月4日(月) の期間、誠に勝手ながら冬季休業とさせていただきます。
- 2020.08.27
- 【お知らせ】事務所移転のお知らせ
- 2020.07.27
- 【夏期休業期間】2020年8月12日(水)~2020年8月14日(金) の期間、誠に勝手ながら夏期休業とさせていただきます。
- 2020.04.02
- 【お知らせ】企業情報を一部変更いたしました。
- 2019.12.04
- 【冬季休業期間】2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日) の期間、誠に勝手ながら冬季休業とさせていただきます。
- 2019.07.31
- 【夏期休業期間】2018年8月13日(火)~2018年8月15日(木) の期間、誠に勝手ながら夏期休業とさせていただきます。
- 2019.04.18
- 【お知らせ】採用情報を更新しました。
- 2018.11.26
- 【冬季休業期間】2018年12月29日(金)~2018年1月6日(日) の期間、誠に勝手ながら冬季休業とさせていただきます。
- 2018.09.13
- 【メディア掲載】「AERA 2018年9月17日増大号」に「週3、4正社員」を掲載させていただきました。
- 2018.08.01
- 【夏期休業期間】2018年8月13日(月)~2018年8月15日(水) の期間、誠に勝手ながら夏期休業とさせていただきます。
- 2017.12.15
- 【冬季休業期間】2017年12月29日(金)~2018年1月4日(水) の期間、誠に勝手ながら冬季休業とさせていただきます。
- 2017.11.21
- 【メディア掲載】webメディア Fledge(フレッジ)に弊社代表を取り上げていただきました。
- 2017.07.25
- 【夏期休業期間】2017年8月11日(金)~2017年8月16日(水) の期間、誠に勝手ながら夏期休業とさせていただきます。
- 2016.12.01
- 【冬季休業期間】2016年12月29日(木)~2016年1月4日(水) の期間、誠に勝手ながら冬季休業とさせていただきます。
- 2016.09.28
- 週3.4 正社員募集をはじめました。
- 2016.07.19
- 【夏期休業期間】2016年8月13日(土)~2016年8月15日(月) の期間、誠に勝手ながら夏期休業とさせていただきます。
- 2015.12.02
- 【冬季休業期間】2015年12月29日(火)~2016年1月3日(日) の期間、誠に勝手ながら冬季休業とさせていただきます。
- 2015.07.13
- 【夏期休業期間】2015年8月13日(木)~2015年8月16日(日) の期間、誠に勝手ながら夏期休業とさせていただきます。
- 2015.03.03
- 採用ページを更新しました。
- 2014.12.10
- 【年末年始のお知らせ】2014年12月27日(土)~ 2015年1月4日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。
- 2014.08.04
- 採用ページを更新しました。
- 2014.05.13
- 企業情報、サービス内容を更新いたしました。
- 2013.12.11
- 【年末年始休業期間】2013年12月28日(土)~2014年1月5日(日) の期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
- 2013.08.12
- 【夏期休業期間】2013年8月14日(水)~2013年8月16日(金) の期間、誠に勝手ながら夏期休業とさせていただきます。
- 2013.04.02
- 事業内容を更新しました。
- 2013.01.12
- コーポレートサイトをリニューアルしました。